
こんにちは、ベーシストのJophoneです。前回ベースのメンテナンスの基本基本編としてボディ乾拭き・弦を拭く等ご紹介しましたので、今回は応用編となります。
弦を外さないと出来ないような事が多くありますので、弦交換のついでにされることをおススメします。
メンテナンスの必要性については前回の記事にてご紹介していますので、もう一度おさらいしたい方はそちらをご覧ください。
メンテナンス応用3選
作業スペースを確保し、ベースを安定させて置く
いきなり作業に入りたいところですが、、、
まずは作業スペースを確保しないといけません。会議用に使われるような長いテーブルがあれば最強なのですが無くても大丈夫です。ニ〇リ等に売ってる折り畳みのテーブルでも全然いけます(‘ω’)
テーブルの上に置く際の重要なことは、、、
・ボディがずり落ちないように接地面を確保する(滑り止めシートがあると最高)
・ギターピロー(ネックを安定させる魔法のアイテム)を使用する。
↳雑誌を重ねたものでも代用できます。固すぎるものはネックに大ダメージなのでNG
フレット磨き

エレキベースのフレット磨きは、弾き心地・音質を整えるための大事なメンテナンスです。
フレットが全てピカピカに反射してるとすごくかっこよくて見栄えもいいですし、大事に使ってるんだなと思わせることもできるのでやって損することは100ないです。
ここからは手順を説明していきます
用意するもの
- マスキングテープ (指板保護用)
- フレット磨き用のコンパウンド (ピカール、フレット磨き用ポリッシュ等)
- 柔らかい布やペーパータオル
- 綿棒 (細かい部分の仕上げ用)
- 指板用オイル (レモンオイルなど)
1. 指板を保護する
※弦交換のついでにという想定なので、弦は全て外されてるものとします。
市販のマスキングテープを使ってフレット周りの指板を隙間なく保護していきます。
フレット磨きの溶液が指板に当たると、木材の油分が奪われて乾燥・割れが起きたり、ツヤや色味が変色・変質する可能性がありますので必ずしっかり保護しましょう。
2. 磨く
1.コンパウンドを布に少量取ります(米粒サイズほどでOK)
直接フレットにつけて磨くよりも、布に付けてから磨く方がコントロールしやすいです。
2. 指で布を巻き、フレットの形に沿って1本ずつ前後に軽くこすります。
強く擦るとフレットが削れ過ぎてしまうので優しく丁寧にやりましょう
3. フレットの端や指で届かない部分は綿棒を使うと綺麗になります。磨かないで放置すると酸化して緑のコケみたいのが出てきたりして汚いのでしっかり磨きましょう。
4. コンパウンドがフレット上に残らないように乾いた布でしっかり拭き取ります。
これでめっちゃきれいになります
3. マスキングテープをはがす
このままでは弦を張れないので、全部はがしていきます。
4. 弦を張る
お好みの弦を張ります。
ここで弦を張る前になんか指板の色が変だな、、ガサガサするなと感じた方は次の
「指板にオイルを塗る」に進んでください。
オイルはいいやぁって方は「ネックの反りチェック」に進みましょう。
指板にオイルを塗る
オイル塗布の必要性
この工程は弦交換ごとにやる必要はありませんが、指板の色が何か変わってきたなぁ、、、なんて思ったり、触って明らかにがっさがさの時にやるのがベストです。
オイル塗布のやるタイミング、もしくはやってはいけないタイミングを下記にまとめてみました。
オイル塗布のやるべきタイミング
- 弦交換のタイミング(3~4か月に1回)
↳交換の頻度が高い人であれば毎回やる必要はナシ - 指板が白っぽくなったりカサついてきたとき
↳特にローズウッドやエボニー(茶色か黒っぽい)指板では油分が抜けると粉拭いたようにかっさかさに - 指板がザラつく・手触りが悪くなった時
↳通常より摩擦が強くなってきたらと感じたらもうそれは保湿待ち - 季節の変わり目(特に冬~春)
空気が乾燥している時期は特にカサカサに
オイル塗布してはいけないタイミング
- 高湿度の梅雨時期
↳外気の湿度が高いので保湿は基本不要、ここで塗りまくるとカビ生えます - 既にツヤっツヤで指板がテカテカしてるとき
↳オイルが浸透しすぎて逆に指板が割れる原因に
用意するもの
- 柔らかい布(Tシャツの切れ端やマイクロファイバー)
- 指板オイル
- 綿棒
step1:まずは汚れを落とす
※弦は外されたものとします。
指板にホコリや皮脂汚れが残っていると、オイルが浸透しません。
なのでまずは乾いた布で指板全体を拭き上げます。
汚れがひどいときは、軽く湿らせた布か、専用の指板クリーナーを使って一度拭き掃除をします。
step2:オイルを布に取り、少量からスタート
布に2~3滴つけて塗っていきます。オイルは少量でも伸びるので、ケチって使うくらいがちょうどいいです。
1フレットずつ木目に沿って円を描くように塗り広げていくと浸透しやすいです。
フレットのきわや溝は、綿棒を使うとしっかり届きます。
step3:5~10分放置
塗った後は自然乾燥させます。ドライヤーなどで乾燥させるのは木材によくないのでやめましょう。
step4:乾いた布でしっかり拭き取る
指板表面に残った余ったオイルを乾いた布で丁寧に乾拭きします。
ベタつきが残るとホコリや汚れが付きやすくなるので、乾いた状態まで拭くのがベストです。
ネックの反りチェック
ネックの反りとは
ネックがまっすぐではなく、、順反り(ネックを横から見ると両端より真ん中が沈んでる)や逆反り(横から見ると真ん中が盛り上がってる)になってる状態のことを「反っている」と言います。これが進むと、
・弦高が高くて弾きにくい
・弦がビビる・音が詰まる
・チューニングが安定しない
などの不具合につながります。
用意するもの
- 六角レンチ(メーカーによってサイズがまちまちなのでセット品があると良い)
- パイプレンチ(六角レンチが使えないタイプのロッドに使用)
- 定規(あると便利)
チェック方法
- 弦を張った状態で見る(これが重要)
↳ネックは弦の張力で自然に反るので、必ず弦を張った状態でチェックします。 - 定規で測る
↳定規(できれば金属の物)で12フレットが真ん中になるように置きます。この時に
「真ん中に隙間ができていたら順反り」「真ん中に隙間がなく両端がカタカタするなら逆反り」です。 - 1弦と6弦でチェック (定規がないときに使えます)
↳ギターを構えた状態で、1弦または6弦に沿ってヘッド側からボディ方向を覗き込む。
この時にネックが「谷のようになっていたら順反り」「山のようになっていたら逆反り」です。
反ってたらどうやって調整する?
ベースネックの中には「トラスロッド」という金属の棒が入っていて、それを回して反りを調整する形になります。ここで「六角レンチ」(またはパイプレンチ)を使って調整する訳ですが具体的に、、
「順反りは時計回し」「逆反りは反時計回し」という感じで回していきます。
どのくらいになるのが良い?
「完全なまっすぐ」より、「少し順反り」くらいに合わせるのがベストです。
まっすぐ過ぎるとスラップでバチバチやるスタイルにはとても弾きやすくていいですが
指やピックで引いたときにほぼ確実にローフレットがビビります。
それが好きという方もいるのでダメとは言えないですがここでは一番オーソドックスなタイプに合わせていきます
調整方法
六角レンチを使って回していきますが
回す時は12時から13時半くらい(1/8くらい)の感覚で回していきます。
一気に回すとロッドが効かなくなる可能性があります。
回したら木が反りの変化に馴染むまで、最低5分は待ちましょう。
まだ反っているかなというときはこの工程を繰り返します。
※弦の張力がない状態なので真っすぐか、ほんの少し逆反りになってるのが良い
調整が終わったら弦を張っていきます。
弦を張った状態で反りを確認してみて、だめなら同じ工程を繰り返します。この時弦は外さなくても緩めておくくらいで大丈夫です。
さいごに
いかがでしたでしょうか?こちらの記事を参考に今後もベースの調整はうまくできましたでしょうか?基本的なポイントを押さえて説明していますので、もしもっと効率のいい方法が自分で発見できたらどんどん試してください。

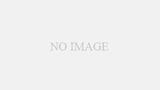
コメント